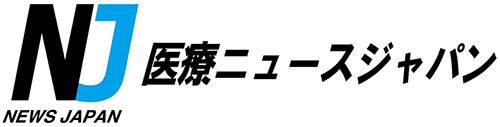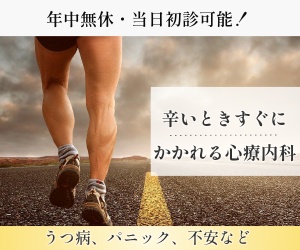「声が枯れる」というのは、よく本や歌など、様々な場面で見るフレーズです。
ドラマチックで良い表現にも見えますが、実はそこには、医療的なリスクが隠されているのです…。
今回は「声が枯れる」症状について、とむせん先生にお話を伺いました!

耳鼻咽喉科専門医
医療や耳鼻科に関するあるあるや豆知識を発信。
ユーモアあふれるコンテンツが人気を博している。
医療や耳鼻科に関するあるあるや豆知識を発信。
ユーモアあふれるコンテンツが人気を博している。
―――「声が枯れる」といえば、歌ったり叫び声を上げたりする等の発声により起こるイメージがあります。このとき喉には何が起きているのでしょうか?
とむせん先生:
発声は左右の「声帯」を使って行われます。
通常の発声ではポリープを形成することは稀ではありますが、強い発声(叫び声など)をした場合に声帯が強く触れ合うことでポリープを形成してしまうことがあります。
こうした発声による血管の破綻が繰り返されることが主な原因と考えられています。
発声は左右の「声帯」を使って行われます。
通常の発声ではポリープを形成することは稀ではありますが、強い発声(叫び声など)をした場合に声帯が強く触れ合うことでポリープを形成してしまうことがあります。
こうした発声による血管の破綻が繰り返されることが主な原因と考えられています。

―――過剰な発声等が血管へダメージをもたらしているのですね。「声帯ポリープ」ができることのデメリットについて、お聞かせいただけますと幸いです。
とむせん先生:
デメリットとしては、自分本来の声が出ないことが主な症状です。
軽症例では、音声治療や薬剤治療などで改善することもありますが、改善がない場合は手術療法を行い、ポリープを切除します。
しかし、その後も再発のリスクがありますので日常生活においても注意が必要です。
デメリットとしては、自分本来の声が出ないことが主な症状です。
軽症例では、音声治療や薬剤治療などで改善することもありますが、改善がない場合は手術療法を行い、ポリープを切除します。
しかし、その後も再発のリスクがありますので日常生活においても注意が必要です。

―――日常的に声の出し方について気をつける必要があるのですね。ありがとうございます。
また、医師としてご活躍される中、先生はご自身の健康を守るためにどんなことを意識されていますか?
とむせん先生:
私が健康を守るために意識していることは「睡眠」です。
睡眠により、日中のパフォーマンスが全く変わってきますので、なるべく日が変わる前に寝るようにしています。
私が健康を守るために意識していることは「睡眠」です。
睡眠により、日中のパフォーマンスが全く変わってきますので、なるべく日が変わる前に寝るようにしています。

―――とむせん先生、本当にありがとうございました!
声の枯れが頻繁に起きている方は、もしかすると今回お話しいただいた声帯ポリープが関係しているかもしれません。
そのままにせず、ぜひ一度耳鼻咽喉科で診察を受けてみてくださいね。
一つしかない自身の喉。日々の意識で大切にしていきましょう。
とむせん先生は他にも、ツイート等にて医療知識をユニークかわかりやすく発信されています。
ぜひチェックください!