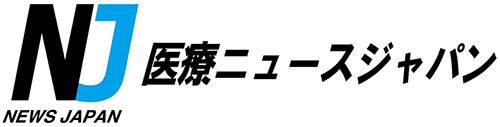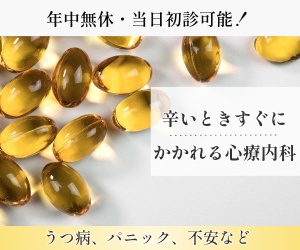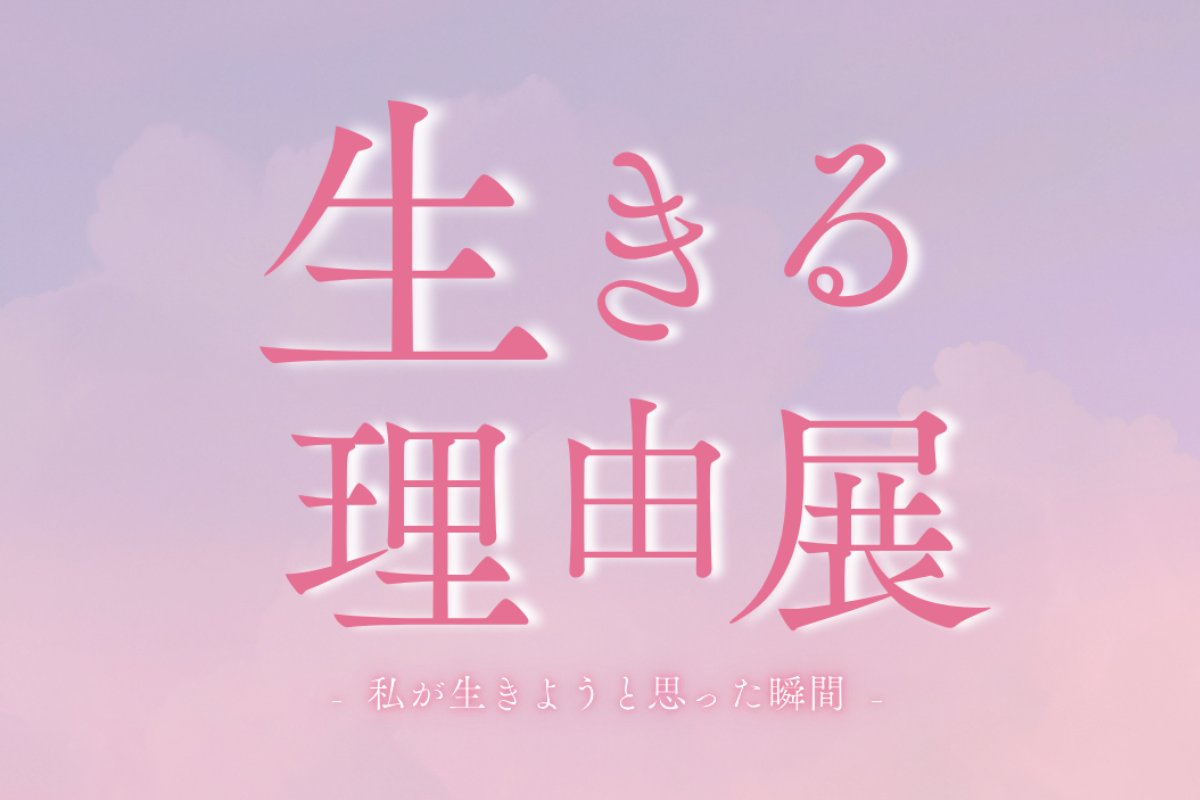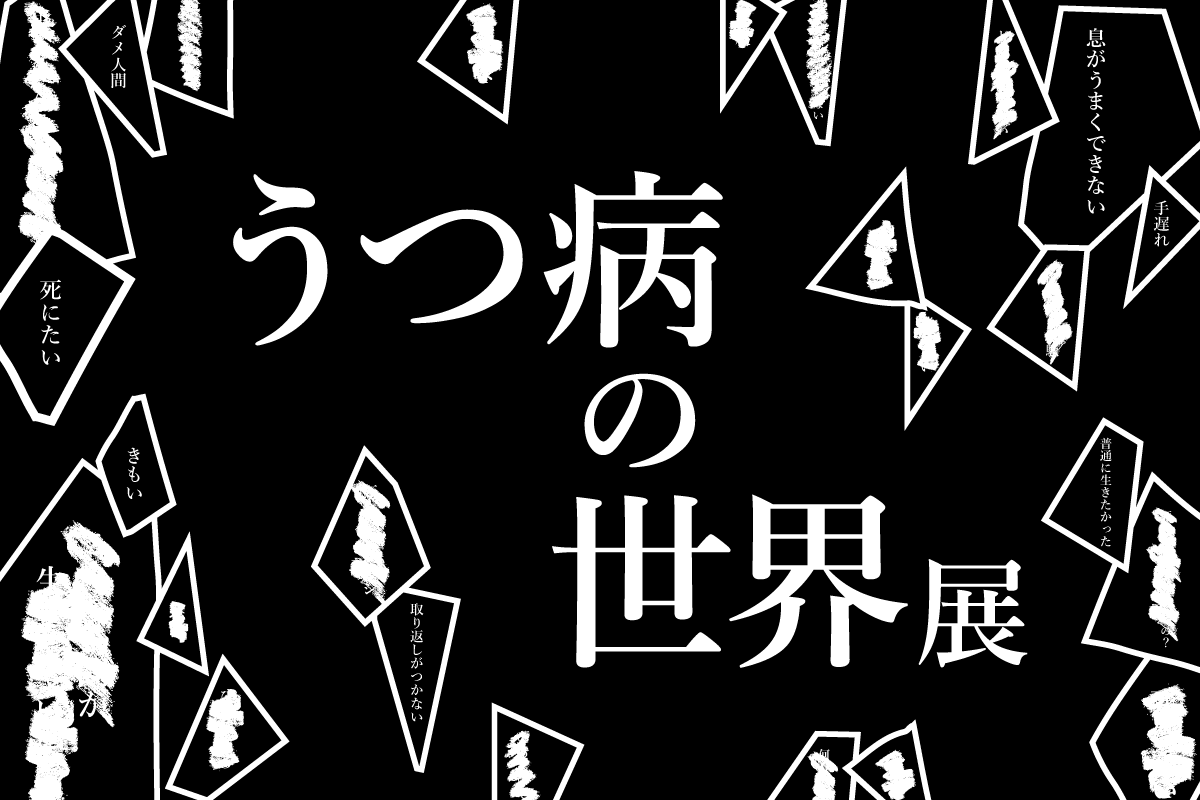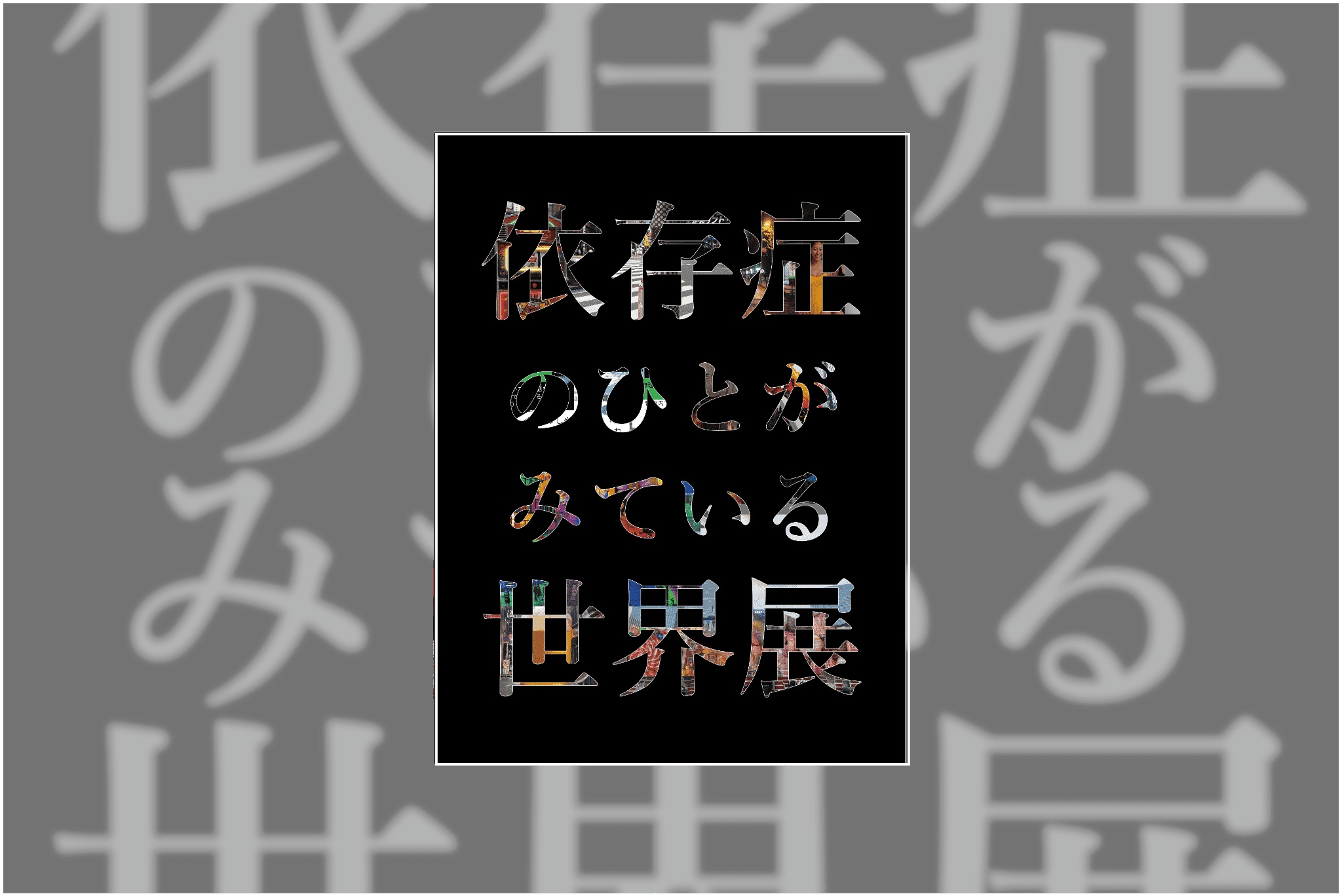高知県警の統計では、県内で昨年補導された少年1733人(前年比224人増)のうち、半数を超える894人(同227人増)が喫煙での補導。
800人を超えたのは7年ぶりだという。
ここまで補導者数が増えた理由として、同課少年サポートセンターは、身近で喫煙している大人の影響や、コンビニ店などでたばこ購入時の年齢確認が本人によるタッチパネルの操作でできることを可能性に挙げる。
また、加熱式たばこやたばこは、現在その高額さから廃棄に本人や保護者の許可が必要になっており、少年たちが保護者の目を盗んで返却されたたばこを吸うなど、再発につながっている恐れがある。
少年の補導や立ち直り支援を行っている同センターは、依存の危険性について知ってもらおうと、昨年は学校などで喫煙や飲酒、薬物の危険性を伝える講義を約165回実施。
担当者は「興味本位で吸い始めて抜け出せなくなる少年もいる。喫煙少年の補導や更生支援とともに、啓発活動にもより力を入れていきたい」と話している。
【ネットの反応】
・タバコって若い頃に吸う習慣ができなければ、その後に30代とかで
新たに吸う習慣はできにくいと思うのよね。未成年をしっかり取り締まるのは大事。
・国が製造、販売をしてる限り、タバコに関する問題が無くなることはない。
・かつてはタバコを吸ってる姿がカッコいい風潮があったが今ではそんなのはもう無い
・少年時代に始める人は、興味本位というか、20歳未満なのに吸ってるぜ~
法律なんかに縛られない俺カッケーみたいなイキがりがあるからだと思う。
元記事はこちら:https://www.yomiuri.co.jp/yomidr/article/20250317-OYT1T50050/